ピアノの椅子は、ピアノや電子ピアノを買われたときについてきたものを、そのままお使いの方が多いかと思いますが、ピアノの椅子には様々な種類があります。
1.背もたれ付きピアノ椅子
 特徴は、高さ調整が素早くできることです。背もたれ付きピアノ椅子は、後ろのつまみだけで自在に高さ調整ができます。教室などで多くの人が使い、高さ調整を頻繁にするのに大変便利です。
特徴は、高さ調整が素早くできることです。背もたれ付きピアノ椅子は、後ろのつまみだけで自在に高さ調整ができます。教室などで多くの人が使い、高さ調整を頻繁にするのに大変便利です。
また、背もたれがあるため、フォルテで演奏する際、体重を前かがみにかけても前に傾くことがなく、安定しています。
背もたれがついていますので、練習に疲れた時に、一休みするのにも便利ですね。

2.背もたれ無しピアノ椅子
 デザインの種類も豊富で、場所もとらないので人気があります。高さ調節は、側面についているネジを回して変えるものが多いです。このため、微妙な高さに合わせることができますが、頻繁に高さを合わせる場合は、背もたれ付きのほうが使いやすいです。
デザインの種類も豊富で、場所もとらないので人気があります。高さ調節は、側面についているネジを回して変えるものが多いです。このため、微妙な高さに合わせることができますが、頻繁に高さを合わせる場合は、背もたれ付きのほうが使いやすいです。

きちんとしたものはフォルテで弾いてもバランスが崩れないよう、どっしりとした重さがあります。高級な椅子は、長時間の演奏でも疲れないよう、座り心地も大変良いです。

背もたれ無しタイプで、一番新しいのがガススプリングタイプ(油圧式)の椅子です。高低がスピーディーにできるし微調整も可能です。
2000年の第14回ショパンコンクールで優勝したユンディ・リは、この油圧タイプの椅子で演奏しました。
演奏会などでは、衣装の邪魔をしないために、背もたれ無しのピアノ椅子を選ばれることが多いです。
3.電子ピアノ用椅子
 電子ピアノとセットで販売されていることが多いです。アコースティックピアノの演奏でも使うことはできますが、簡易に作られたものが多く、重厚なものはありません。そのかわりに、電子ピアノの色に合わせやすい色の椅子が多く販売されています。
電子ピアノとセットで販売されていることが多いです。アコースティックピアノの演奏でも使うことはできますが、簡易に作られたものが多く、重厚なものはありません。そのかわりに、電子ピアノの色に合わせやすい色の椅子が多く販売されています。

いろいろなタイプの椅子がありますが、あくまでも椅子は演奏のためにあります。体重をかけて激しく演奏しても傾かず、しっかりしているもの、高さ調整がしやすいもの、座り心地の良いものを選びましょう。
ピアノは、どなたでもポンと鍵盤をたたけば、音が出ます。しかし、左右の10本の指を駆使し、美しい音で演奏するには、指の曲げ方、手の形や置き方が大切になってきます。
ピアノを弾く時の理想的な手の形は、自分が鍵盤を押したいと思った時に、思い通りに指を動かせる形、いつでも指が動かせる準備の形です。
それには、無理のない自然な形であるべきです。不自然な形で演奏して、指や手首が痛くなってはいけません。
では、自然な手の形は、どのようなものでしょう?
立って腕から力を抜いてみると、自然に指が内側に向いています。この形が、自然体の手の形です。自然体ということは、力が入っていないリラックスした状態です。リラックスしていることで、手は本来の動きができるのです。
ピアノを弾くときも、この自然体の手の形が基本になります。

①両手を合わせます。
お祈りするように、ぴったり両手を合わせましょう。

②手を膨らませます。
次に、親指はそのままで、親指以外の指の指先は離さずに膨らませるようにします。

このバランスの整った状態が、ピアノを弾く時の手の形になります。合わせている手を離して、そのままの形でピアノの鍵盤においてみましょう。この手の形が基本的なピアノを演奏するときの手の形になります。
自然な手の形で、きれいな音でピアノを奏でたいですね。
でも、小さいお子さんの場合、まだ手の骨が十分に発達していませんので、無理をしないで、あせらずゆっくり綺麗な手の形を作っていきましょう。
ピアノは楽器の王様といわれ、世界中で愛され親しまれ、演奏されている楽器です。
その魅力を探ってみましょう!
ピアノは鍵盤楽器ですので、きちんと並んだ鍵盤によって、音の高低や音の並びが小さな子供さんにも分かりやすくなっています。
慣れてくると、指が鍵盤の位置を覚えて、音階も理解しやすいです。

フルートのような管楽器やヴァイオリンのような弦楽器は、楽器の正しく美しい音を出すのは容易ではありません。挫折してしまう人も少なくありません。
一方、ピアノは鍵盤を押すだけで、ピアノの音が鳴ります。ですから、はじめて親しむ楽器として最適といえます。将来、他の楽器を習うにしても、ピアノの基礎があると、スムーズに入っていくことができます。
ピアノの演奏は両手を使い、片手でメロディーを、もう片方の手でそのメロディーの伴奏をというように、同時に楽しむことができます。
メロディー、ハーモニー、リズムという音楽の3要素を1台で学ぶことができるのです。
ピアノは、オーケストラのすべての楽器をカバーする7オクターブと4分の1の音域を持っています。オーケストラで一番低いコントラバスより低い音も、一番高いピッコロよりも高い音が出せます。また、重厚な響きも軽快な響きも合わせ持っていますので、様々な楽器の音色を弾き分けることができます。
そのため、オペラやバレエの練習のときには、ピアノがオーケストラの代わりを務めています。

ピアノは指先のタッチで、音にさまざまな表情をつけることができます。タッチで音に感情を込めることができるのです。
また、グランドピアノでは、ペダルの効果により、多彩な音の変化をつけることができます。
ささやくようなピアニシモから嵐のようなフォルテシモまで、音の強弱の幅(ダイナミックレンジ)が大変豊かです。
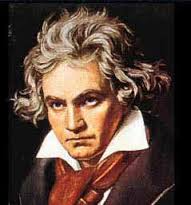
1709年、イタリアでピアノの原型が発明されて以来、300年のピアノの歴史は、音楽の歴史と重なります。
バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、ショパン、リストなど大作曲家たちは、すべてすぐれたピアニストでありました。そして、ピアノ曲だけでなく、交響曲などもピアノを使って作曲しました。ピアノの幅広い表現力が、作曲家の創造力を育んだのです。
このように、魅力溢れるピアノ。世界中で親しまれているのには、理由があったのですね。
アコースティックピアノ、つまり、生のアップライトピアノやグランドピアノは、指先で鍵盤を押し、その力でハンマーを動かし、弦を叩いて音を出します。ハンマーが弦を打つことによる振動が響板を伝わり、音が豊かに広がります。同時に、たたいた弦以外の弦も共鳴し、独特の響きを生み出しています。
一方、電子ピアノには弦が存在しません。鍵盤は、音を出すためのスイッチで、打鍵を感知し、電子音源を発音させ、スピーカーで音を増幅しているのです。電子ピアノは、電気製品なのです。

アコースティックピアノは弾き手のタッチにより、音色が無限に変わり、曲想をつけて表現豊かに弾くことができます。乱暴に叩けば乱暴な音になりますし、やさしく押せば繊細なやさしい音になるのです。
電子ピアノは、鍵盤を押す強さは基本、音量の差にしか表れません。どのように弾いても、音色が変わることはないのです。
電子ピアノもテクノロジーの進歩の伴い、アコースティックピアノに、より近い音の再現が可能になってきました。鍵盤のタッチも、生のピアノに近くなるよう様々な工夫がされてきています。
しかし、電子ピアノでは豊かな表現が難しいことが多いのも事実です。特に、フレーズの終わりの響きを聴いたりスタッカートの切り方をタッチによって変えることなどが難しいと思います。レッスンで学んだことが電子ピアノではできないこともあるかもしれません。
楽器の購入をお考えの際は、価格だけを見てお考えにならず、是非ご相談くださいませ。ご一緒に、より良いピアノライフを考えたいと思います。

ピアノといえば、本来はグランドピアノをさします。
 アップライトピアノは、設置する面積が限られている場所でもピアノ演奏が楽しめるように、グランドピアノでは水平に貼ってある弦を、縦に張ってコンパクトにしたピアノです。このように、グランドピアノが本来の形で、その構造からもより豊かな表現が可能になっています。
アップライトピアノは、設置する面積が限られている場所でもピアノ演奏が楽しめるように、グランドピアノでは水平に貼ってある弦を、縦に張ってコンパクトにしたピアノです。このように、グランドピアノが本来の形で、その構造からもより豊かな表現が可能になっています。
グランドピアアノとアップライトピアノは、大きさや形以外にどんなことが違うのでしょう?
大きな違いは、弦を水平に張るか縦に張るかの違いから生じるアクションの構造の違いです。
アクションとは、鍵盤を押す上下運動を弦をたたくハンマーの打弦運動に換える機構のことです。演奏者の指の動きを現に伝えるための装置で、ピアノの頭脳とも言える重要なものです。

そのアクションが、グランドピアノの場合はハンマーは下から弦をたたくため、ハンマーの自重で元に戻ることができます。ですから、トリルなどの速い連打もスムーズにできます。1秒間に約14回連打が可能です。

一方、アップライトピアノは、ハンマーで弦を横からたたくため、ハンマーをスプリングで元に戻します。トリルなどの連打には限界があります。1秒間に約7回程度です。
ピアノには、3本のペダルがついています。機種によっては2本のピアノもあります。

右ペダルがダンパーペダルで、グランドピアノもアップライトピアノも、鍵盤から指を離してもダンパー(弦の振動を押えて音を止める働きをします。)は戻らず、弦を長く振動を続けます。
グランドピアノの場合、真ん中がソステヌートペダルです。直前に押した鍵盤のダンパーだけが弦から離れますので、その音だけが余韻として残ります。アップライトピアノには、この機構はありません。アップライトピアノの真ん中のペダルは、マフラーペダルと言って、ハンマーと弦の間に薄いフェルトが下りてきて、音量を下げる働きをします。
グランドピアノの左ペダルは、シフトペダルです。これを踏むとアクション全体が右にスライドします。3本の弦を叩いていたハンマーが2本に、2本の弦を叩いていたハンマーが1本だけになり、音量と音色に変わります。アップライトピアノでは、スライドしません。左のソフトペダルを踏むと、ハンマーが弦に近づき音がソフトになります。
このように、グランドピアノとアップライトピアノには、構造上の様々な違いがあり、同じように演奏しても表現に違いが出てきます。
お家にグランドピアノがある方は少ないと思いますが、本来のピアノの響きや音色を味わうために、機会があれば是非、グランドピアノをお弾きになってみられることをお勧めします。
たとえ、ピアノを始められたばかりの小さなお子様でも、その美しい響きに耳をすましてくれるでしょう。
誰もが知っている「ねこふんじゃった」。ピアノで遊びながらお弾きなられた方も多いと思います。
この「ねこふんじゃった」は、誰が作曲したのでしょうか? そもそも、ピアノ曲でしょうか?
「ねこふんじゃった」は、作曲者不詳といわれています。発祥国もわからないようです。ピアノ独奏されることが多いですが、多くのアレンジやバリエーションもあります。
楽譜では、♯あるいは♭が6個もつく(変ト長調もしくは嬰ヘ長調)ため、とても難しそうに見えますが、実際に弾いてみるとわりに単純です。ピアノを習っていない人も、楽譜が読めなくても、少し練習すれば弾けてしまいます。覚えやすくてコミカルなメロディと知名度の高さから、大変親しまれていますね。

日本では、NHKの『みんなのうた』で阪田寛夫が作った歌詞が使われ、広く歌われていますが、「ねこふんじゃった」は日本独自の曲名で、世界の国や地域ごとに様々な歌詞や曲名がつけられています。
♪ねこふんじゃった(日本) ♪ねこのマーチ(ブルガリア) ♪ねこの踊り(韓国)
♪子猫之舞 (台湾) ♪黒猫のダンス(ルーマニア) ♪猫のポルカ(フィンランド)
♪犬のワルツ(ロシア) ♪犬のポルカ(チリ)
♪蚤のワルツ(ドイツ、ベルギー) ♪ノミのマーチ(オランダ、ルクセンブルグ)
♪アヒルの子たち(キューバ) ♪三羽の子アヒル(キューバ)
♪ロバのマーチ(ハンガリー) ♪お猿さん(メキシコ)
♪豚のワルツ(スウェーデン) ♪トトトの歌(イギリス、アメリカ)
♪カツレツ(フランス) ♪チョコレート(スペイン)
♪公爵夫人(デンマーク) ♪三女の足(デンマーク)
♪道化師ポルカ(アルゼンチン) ♪追い出しポルカ(マジョルカ島)
♪箸 Chopsticks (イギリス、アメリカ、カナダ、ハンガリー)
♪黒のメロディー(ユーゴスラビア) ♪サーカスソング (イギリス、アメリカ、カナダ)
♪泥棒行進曲 (中国)
動物や食べ物など、とってもバラエティーに富んでいて面白いですね。
「蚤のワルツ」てどんな感じかなといろいろ想像しながら「ねこふんじゃった」を弾いてみると、ますますピアノが楽しくなりますよ。
昨年10月に「ミキハウス子育て総研」が調べたところ、子供の習い事の1位は「ピアノ」で29.9%、2位が「水泳」で28.7%。3位は「英語・英会話」で17、2%でした。「ピアノ」と「水泳」が人気というわけですね。
1つだけ習わせるとしたら、どちらがよいのでしょうか?
日刊ゲンダイが伝えるところによりますと、教育評論家の尾木ママこと尾木直樹氏は、「ずばり“ピアノ”です。両手を使い、譜面を見て、耳も暗記力も使う。脳の司令塔である前頭前野を鍛え、地頭を強くします。IQならぬ『HQ』を上げるのにも役に立ちます。」とお答えされたそうです。
HQとは、Humanity Quotientの略で、「人間性指数」のことです。単なる頭の良さだけでなく、社会性や感情表現なども能力を測る指標にしようというものです。
「HQが低いと、自分で意思をもって行動できず、喜怒哀楽もはっきり表せない。人とのかかわりが持ちづらくなり、やがて社会から脱落していきます。グローバル社会の今、大事なのは自分の意思をもって様々な人とコミュニケーションすることです。これは世界の常識なのですが、日本ではまだ真剣に議論されていません。大変遅れているのです!」

明石家さんまさんが司会を務める「ホンマでっか!?TV」に出演されている脳科学者の澤口俊之先生も、習い事の質問に対して、「1番習い事としていいのはピアノです。指を動かす、先を読む、暗記する。全て脳の働きを高める。ピアノを習っている子は頭がいい。さらに、ピアノを習うとキレにくくなる」とお答えされています。
教育の専門家や脳科学者の先生方がお薦めされる「ピアノ」を、大切なお子様のためにお考えになられてはいかがでしょうか?

古矢ピアノ教室には、大人の方もレッスンに来て下さっています。
40代から80代の方までいらっしゃいます。
「生徒さんの声」でご紹介しましたI様(80代 女性)は、2年前にご主人様を亡くされましたが、介護中もずっと、ピアノを続けてこられ、今も、毎日、音の世界を楽しんで下さっています。
「譜面を読んでも指がなかなか覚えられなかったり、強弱がつけられなかったりと悪戦苦闘の中、それでも昨日より今日、今日より明日と、頭の体操を繰り返しながら楽しい時間を過ごしています。」とお書きくださっています。
その一途で、一生懸命なお姿に、いつも頭が下がる思いがいたします。
1年3ヶ月前からレッスンにお越し下さっていますN様(70代 女性)は、
「以前ならった曲をみていただいています。とても優しい先生で丁寧に指導していただいております。大きなグランドピアノを弾けるのも魅力です。」とお書きくださっています。
また、40代の女性、W様は、お仕事でお忙しい中、お時間を作ってピアノを練習され、レッスンに通ってきてくださいます。
先日、ご入会されました60代男性、N様は、「いろいろな趣味を楽しんできましたが、長年、憧れだったピアノを最後の趣味として楽しんでいきたいです。」とお話し下さいました。
大人の方は、ピアノが全く初めての方、以前、少し習っておられた方、また、いろいろな名曲をお弾きになる方と様々な方がいらっしゃいますが、皆様それぞれ、生涯の楽しみ、趣味としてご自身のペースでピアノをお弾きになり、音楽と共にある生活を楽しまれています。
個人レッスンですので、初心者の方もマイペースで安心してレッスンをお受けいただけます。
ご一緒に、音楽で心に花を咲かせませんか?

黒鍵36鍵、白鍵52鍵、合わせて88鍵あります。これは、グランドピアノもアップライトピアノも変わりません。電子ピアノも88鍵です。
ただし、ベーゼンドルファーの「インペリアル」と呼ばれる最上位機種のフルコンサートピアノのみ、通常の88鍵に加えて低音側に9鍵加えて、合計97この鍵盤があります。この拡張部分は、現在は、演奏者が間違わないように全て黒色に塗装されています。

これは、プゾーニがバッハのオルガン曲を編曲した時に、低音部にピアノでは出せない音があったため、ベーゼンドルファーが鍵盤を追加したのが始まりとされています。この9鍵が追加されたことにより、弦の響板が広くなり、共鳴する弦も増えて中低音の響きが豊かになっています。
一般の白鍵はアクリルが主流で、高級機種は象牙です。最近は、人工象牙も増えてきました。木で作った鍵盤の表面に象牙やアクリルを貼ってあります。
黒鍵は、普及機種はアクリル、高級機種は黒檀が使われています。人工象牙を黒くしたものを使っている機種もあります。
象牙は、演奏時に汗をかいても滑りにくいのが大きな特徴です。指を置いた時に、吸着した感じも特徴で難易度の高い曲は象牙のほうが弾きやすいと言われています。しかし、ワシントン条約が発効されてから、象牙の流通が禁止となり、残念なことに今ではコンサート用のグランドピアノも象牙が使えなくなっています。

また、昔は象牙のほかに、動物の骨も使われていたそうです。昔は流通の関係でこれらの白鍵素材が黒檀に比べて手に入りにくかったため、白黒の配置が逆だったと言われています。

古矢ピアノ教室のピアノは2台ありますが、どちらも象牙と黒檀の鍵盤で、とても弾きやすいですよ。

海外のピアノメーカーは、世界三大ピアノメーカー以外にもたくさんあります。
その中でも、日本にも輸入されているピアノを一部ご紹介いたします。
ファツィオリ
1981年創業のイタリアのピアノメーカーです。綿密な手作業を徹底し、世界で最も高額なピアノとして知られています。
スタンウェイが年間数千台生産される中、ファツィオリは、年間130台ほどの少量生産です。
透明感のある温かみのある音色や響きが特徴で、最高級のイタリア職人の技術と相まって、昨今、日本でもピアノ愛好家の中で高く評価されています。

ペトロフ
1864年創業のチェコのピアノメーカーです。伝統を守りながらピアノ制作をしていますので、品質が良いうえに、ヨーロッパ製ピアノにしては生産台数が多く価格も抑えめになっていますので、日本でも人気があります。
高品質で良心価格を実現していますので、調律師やプロのピアノニストからも評判は良いです。
音色や響き、デザインの美しさなど、国産ピアノにはない奥の深い魅力をもっています。

ザイラー
1849年創業のドイツのピアノメーカーです。透明感のある明るい音色が特徴的で、数々の賞を受賞しています。
ザイラー社は、ドイツピアノ品質保証表記協会から、すべてのピアノに「品質保証シール」をつけることを認められた唯一のピアノメーカーです。

シンメル
1885年創業のドイツ最大手のピアノメーカーです。一般向けの普及品ピアノを大規模に生産しています。
また、小型のアップライトピアノを開発し、クリスタルのピアノや斬新なデザインのものなど多種多様なピアノを世に送り出しています。

ボールドウィン
1873年創業のアメリカのピアノメーカーです。
1900年のパリで開かれた万国博覧会でグランプリを受賞し、有名なピアノメーカーになりました。
表現力が豊かな音質で、弾きやすいピアノと言われています。

国内外、様々なピアノメーカーがありますね。それぞれ歴史や特徴があり、興味深いです。
機会があれば、是非、いろいろなピアノを弾き比べてみたいものです。
Copyright © 2018 Furuya Piano School All Rights Reserved.